top of page


ロードバイクという趣味Ⅰ
建築の設計という仕事は求められる知識がとても多く仕事を進めるにあたってストレスがたまりやすいです。 また、体力勝負みたいなところもありますので仕事とは関係のない趣味の時間は大切だと思ってます。 幸い夫婦共通の趣味としてロードバイクがあり、近所の友人とチームを作り遊んでいます。 そんなわけで、施主さんがロードバイク乗りだと当然のことながらテンション上がります。 ロードバイクは速く走るという機能を追求した機能美を持っていて、いろいろな景色に映える乗り物です。 建築も住むための機能と美しさを兼ねそろえたものでありたいと思っています。


ロードバイクという趣味Ⅱ
ロードバイクはよくできた乗り物で、少ない力でより速くより遠くへ行くことができます。 また、車では入れないところへ行けたり、車のスピードでは気づけない景色を感じたりできます。 今までいろいろなところへ連れて行ってくれました。 淡路島ツーリング 58.0km 自転車モニュメントがある岩屋港を発着とし、淡路島の北部を時計回りにサイクリング。 和歌山ツーリング 24.2km 串本駅からサイクルトレインで太地駅まで行き、そこから串本まで海沿いの道をサイクリング。石切岩、橋杭岩など。 博多湾ツーリング 53.0km 博多の中心地をスタートし海の中道経由で志賀島を一周し、船で博多港へ渡りスタート地点へ。 安曇野ツーリング 48.5km 長野県安曇野の各地を巡るサイクリング。 いわさきちひろ美術館や碌山美術館など。 奈良ツーリング 54.1km 天理付近をスタートし東部のまほろばの道を南下し石舞台古墳、高松塚古墳などをめぐりゴール地点へ。 東京ツーリング 45.5km 清澄白河~皇居~神宮~代々木~新宿~早稲田~後楽園~上野~浅草 東京って大都会だけど自転車で走


コロンボと建築設計
好きな映画のかなり上位に 刑事コロンボ があります。 なぜ好きなのかというと、まず犯人がわかり、それをどうやってコロンボが追い詰めていくかというわかりやすいストーリー展開と、最後になるほどとスッキリして終われる安定感なのだろうと思います。 設計の仕事も最終的な姿が明快にみえていて、それにむかってわかりやすく安定感のある進め方ができるとよいと思っています。 実際には試行錯誤の連続ですけど… まあ、コロンボもみえないところで試行錯誤の連続なんだろうと思いますので…


将棋と建築設計
プロの将棋をプロの解説付きで見るのが好きないわゆる「観る将」で、日曜の午前中家にいればだいたいNHKの将棋を見てます。 実際に指すことはないですが3手詰めを考えるのは好きです ^^; 将棋に序盤・中盤・終盤があるように、建築設計には構想段階(序盤)・基本設計段階(中盤)・実施設計段階(終盤)があります。 構想段階であらゆる可能性の中から進むべき方向を見いだし、基本設計段階で具体的にプランにあてはめていき、実施設計段階で細かな部分を考え抜いて設計をまとめあげます。 将棋の棋士の人たちが序盤・中盤のなんでもないような場面で数十手先、場合によっては詰みまで読んで長く考えているように、建築設計でも完成して人がその中でどのように動くのかまでしっかり考えて構想段階から進めていかなくてはいけません。 こんな感じで、将棋と建築設計はにたところがあると思っています。


ホームページ作りのこと
このホームページは、2002年に始めて以来試行錯誤を重ねながらすべて自分たちで作ってきました。 当時はホームページを持つ設計事務所はまだまだ少なかったですが、今はホームページがあるのがあたりまえとなっています。 プロが作るようなすごい技があるわけではありませんが、一生懸命誠実に作れば何か伝わると信じて試行錯誤を今も続けています。 このホームページを見て少しでも興味を持っていただける方がいらっしゃればぜひ声をかけてくださいね。


設計者に求められること
建築設計という仕事は広く浅く(時として深く)いろいろな知識や役割を求められます。 ある時はデザイナーとして、斬新なアイデアを求められ… ある時は技術者として、専門的なアドバイスを求められ… ある時は法律家として、的確な判断を求められ… ある時はコーディネーターとして、適切な調整能力を求められ… これらの(ある意味)相反する能力を身に付けることはかなり大変なことなんじゃないかと思いつつ頭が固くなりすぎず柔らかくなりすぎないよう日々精進しています。


送料無料・設計料無料のお話し
以前、箱根駅伝で応援する人が多くて配達先の近くに車を停められない宅配業者さんが荷物をかかえて箱根のランナーと同じくらいのスピードで走っている姿があった… というエピソードがあり、このとき思ったことです… 通販番組等で「送料無料」などと大きく叫んでいるのがあるんですが、商品を時間どおりにとどけるために必死になって走っている人がいてその人には給料が払われているのだからあきらかに「送料無料」というのは嘘で、自分には宅配業者さんを「宅配なんてたいしたことないからただでいいよ」とバカにしているようにさえ感じられます。 にたようなことで、 ハウスメーカーなどの宣伝で「設計料無料」と叫んでいるところがあります。 建物をつくるためにはお客さんの意向を聞いて図面を描き、許認可をとるという重要な仕事をしている「設計者」がかならずいて、もちろんこの人たちにも給料が払われているのだから、「設計料無料」というのももちろん嘘で、設計を生業としている自分は「設計なんてたいしたことじゃないからただでいいよ」とバカにされているようで嫌な気持ちになります。 なぜこのような宣伝方法が


サザエさんの家についての考察
国民的一家のおうちについてまじめに考えてみました。 古き良き時代ならではの部分と現代でも通じる部分があると思います。 建築概要 用途:一戸建ての住宅(二世帯住宅) 構造:木造 平屋建 面積:約122㎡(37坪) 家族構成 親世帯(磯野家) 夫婦(ナミヘイとフネ)+子供二人(カツオとワカメ) 子世帯(フグ田家) 夫婦(マスオとサザエ)+子供一人(タラ) 若夫婦の奥さんの実家での同居なので、いわゆる嫁姑問題などは心配ないパターンです。 マスオさんの優しい性格もあって同居がうまくいっていると思います。 サザエさんの家平面図 [マスオ・サザエ・タラの部屋] 南東の一番良いところにあり、ナミヘイとフネの娘夫婦に対する愛情を感じます。 親の部屋と離れており、兄弟の部屋とも廊下をはさんでますのでプライバシーが守れるよう配慮されています。 ただ、布団を入れる押し入れの幅が狭いのが残念です。 [ナミヘイ・フネの部屋] 大きな床の間と飾り棚がある立派な部屋になってます。 ナミヘイがカツオたちをしかる時に父の威厳を示すのにはよいですが、寝室をかねることを考えるとやは

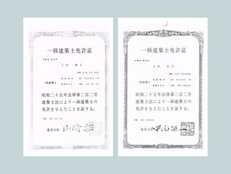
一級建築士の免許証について
一級建築士の資格は国家資格となりますので、その免許証には大臣の名前が載ります。 今なら国土交通大臣となるのでしょうが、私たちの時代は建設大臣でした。 当時は免許を取ればその後何もなかったのですが、今は3年に1回の講習を受けその後行われるテストに合格しないといけなくなりました。(理由は…建築士が関与する事件があったから) まじめにやっていれば大丈夫なのですが法改正などが多く建築士を取り巻く状況は年々厳しくなってます。 でも、好きなことなので頑張れます。


大学の卒業設計のこと
自分の大学の建築学科では4年生の最後に卒業設計というのがあり一等賞は村野賞(建築家の村野藤吾先生からとられた名前)とよばれ設計を志す学生はこれを目指して頑張っていました。 自分はこの卒業設計のタイトルに “色彩都市” とつけ、 「都市は建築という色彩に彩られた楽しい場所であってほしい」 などと書きました。 実はこの理由は後付けで、当時好きでよく聞いていた大貫妙子さんのこの曲名がすごく印象的でここから拝借した次第でした。 もう時効です・・・ ^^; 後付けの理由ではありましたが、今でもなんとなくですが、 「都市は建築という色彩に彩られた楽しい場所であってほしい」 と思いながら設計しているような気がします。 村野賞!とはいきませんでしたがまあまあの成績でしたよ ^_^


建前という幸せなひと時
建物をつくるのにはいろいろな過程がありますが、やはり建前の時が一番胸躍る感じがします。 地鎮祭の時は「さあこれから頑張るぞ!」という気持ちはありますがまだ何もできてません。 竣工の時は達成感はありますが、終わってしまうというなにかさみしさがあります。 それに対して建前はそれまで考え続けてきたことがいっきに形になり嬉しいと同時に改めて「ますます頑張るぞ!」という気持ちがわいてきます。


手の痕跡を残す
時としてコストダウンのために、あるいは自分の思いを表現するために施主さん自ら工事をすることがあります。 壁に珪藻土を塗ったり、ペンキを塗ったり、土間に石やビー玉を埋め込んだり、木を植えたり・・・ プロの職人さんのようにはいかなくても職人さんには出せない「あじ」が出たりしていいし、なによりも自分が住む家に手の痕跡が残りいい思い出になります。


絵画のように平面図を楽しむ
よく考えられた平面図というのは絵画のように美しいと思っています。 そんなわけでいろいろな色を付けてみました。 たんなるお遊びです... ^^;


インスピレーション
ふとした瞬間になにかを感じる風景に出会うことがあります。 光と影の組合せであったり、素材の組み合わせであったり、色の組み合わせであったり… そういったことを感じ取れるような感性を持ち続けていきたいと思っています。


代々木体育館のこと
記憶がさだかではないのですがおそらくまだ子供の頃にモノクロのかっこいい建物の写真を見た記憶があります。 だいぶ後になってから、それがおそらく代々木体育館だったのだろうと気づくわけで、この写真を見たことで自分が建築の道にすすんだのかどうかはわかりませんが、今でもかっこよくて好きな建物です。 たぶんこの写真のような気がする https://collection.topmuseum.jp/Publish/detailPage/22244/ ロードバイクでまわりを走った時の動画


伊東豊雄建築ミュージアムのこと
伊東豊雄建築ミュージアムはしまなみ海道で有名な瀬戸内海にうかぶ大三島にあります。 詳しくはこちら → http://www.tima-imabari.jp/ ここは建築が素晴らしいのはもちろんですが、そのロケーションやまわりに展示されている作品がとてもよかったです。 伊東豊雄さんが設計された建築のコンセプトモデル(という言い方でよいのでしょうか)がスチールで作られていました。 建築設計をやってらっしゃる方であればどこかで見たことがある気がするのではないでしょうか? サイクリストの聖地(しまなみ海道)らしくおしゃれなサイクルスタンドもありました。


外観づくりの練習
トレーニングで作った四角い箱を基調としたいろいろな外観です。


グーグルアースで建築の旅
今は便利なものでグーグルアースを使えば世界中どこへでも行けて建築を見ることができます。 自分が訪れた場所を中心に興味はあるが行けなかった場所も加えてつくってみましたので興味のある方は旅をしてみてください。 ・目次の中の場所(選択したアイテムに合わせてズームする)をクリックするとそこへ行けます ・3Dボタンを押すと立体的になりぐるぐる回ります


建築とスケッチⅠ(ヨーロッパ)
まだ事務所を始める前なのでだいぶ昔のことになりましたが、ヨーロッパのいろいろな建築を見てまわる機会にめぐまれました。 当時、首に一眼レフカメラとコンパクトカメラをぶら下げて、手にはガイドブックとスケッチブック、ポケットには予備のフィルムを入れるといういでたちで動きまわってました。(今ならスマホ一台あればだいたい事足りますね) 移動中にガイドブックで情報を確認して、現地に着いたらとにかくいろいろ見て写真を撮り、時間がある限りスケッチをして... の繰り返しでかなりハードでしたが、とても貴重な体験でした。 オタニエミ工科大学(アアルト大学) 場所:フィンランド エスポ― 設計:アルヴァ・アアルト ル・トロネ修道院 場所:フランス ル・トロネ 設計:--- コロニア・グエル教会 場所:スペイン バルセロナ 設計:アントニオ・ガウディ バルセロナパビリオン 場所:スペイン バルセロナ 設計:ミース・ファン・デル・ローエ 旅先のスケッチ モスクワ空港・ヘルシンキの街・南フランスの街 以下、見ることができた建築のリストです。自分自身の覚書として... フィン


建築とスケッチⅡ(コルビジェ)
ヨーロッパで見てまわった建築の中でもやはり(自分の中では)コルビジェは別格であったと思います。 ロンシャンの教会|フランス|ロンシャン ラトゥーレット修道院|フランス|リヨン ユニテ・ダビタシオン|フランス|マルセイユ サヴォア邸|フランス|ポアシー


アンビルド 街や川とつながる公園建築
お城と川をはさんで向かい合う敷地にある子どものための活動・交流・発表のための施設で外部はすべて一般に開放された都市型公園。 階段状の屋根 ~ ひろば ~ 階段状の堤防の斜面 ~ 河川敷 をすべてウッドデッキで作った川と一体となった公園。 右側の白い四角い箱はおしゃれなカフェと絵本図書館とその読み聞かせができるスペース。 左側の白い円筒形はだれでも自由に弾けるグランドピアノがあり、そのまわりはギャラリーで若手芸術家の発表の場。 手前の半円形のスペースは路上ライブやパフォーマンスの場。 幹線道路ともゆるやかにつながる都市型公園で自由に出入りできる。 三角形のシンプルで力強い彫刻的な建築。 ひろばにはウッドデッキをくりぬくように作られた芝生のお山や水遊びできる噴水があり、あちらこちらに触ることができるアート作品や遊具が点在している。 上の方についている赤い球体は2人ぐらい入れる大きさで小さな穴がいくつかあいていて覗くとお城や橋なんかが見えたりする「TENBOUDAI」というアート作品。 階段状の木でできた屋根はお城や川をながめたり夏の花火大会の客席にも


アンビルド 自然にとけこむカフェ
山の上の森の中の緑に囲まれたカフェです。 まわりの自然に溶け込むシンプルな片流れ屋根です。 景色を最大限取り入れるよう連続した窓がL型に配置されています。 客席は無垢の木をふんだんに使ったインテリアになっていてテーブル席・カウンター席・ハンモック席・個室など様々な楽しみ方ができるようになっています。


アンビルド 変形敷地に建つ家
変形敷地という厳しい条件でありながら、ビルドインガレージや内玄関のある玄関、部屋と庭をつなぐウッドデッキなど特徴的な空間をとりいれ暮らしやすい家としました。 [ビルドインガレージ] 玄関を出て雨にぬれずに車に乗ることができます。 [内玄関] 家族は玄関からつながる内玄関から入りますので、子供が靴を脱ぎ散らかしても玄関はスッキリしてます。 また、この内玄関は収納を兼ねてますので色々なものを置くことができて便利です。 [いろいろそろったダイニングキッチン] アイランドキッチンの横に食卓があり家事動線が短くてすみます。 子供のためのスタディコーナーがあり世話をしながら家事ができます。 洗面コーナーが内玄関から入ってすぐのところにありすぐ手洗いやうがいができます。 リビングとは戸で仕切ることができるので来客時に便利です。 [ウッドデッキ] ウッドデッキを囲むようにダイニングキッチンと和室がレイアウトされていて非常に使いやすくなってます。 切妻屋根と水平に伸びた屋根の下にガレージが組み込まれています ざらっとしたベージュの土壁とこげ茶色の格子や柱の組み合


アンビルド 宿泊施設にもなる住宅
非常に眺めのよい敷地に建ち宿泊施設としても使えるように考えられた住宅です。 眺めのよい方向に大きな開口とウッドデッキを設けています。 玄関土間~リビング・ダイニング~個室とつながる空間を一体的にも、仕切ることもでき、さまざまな使い方に対応できるようになっています。 天井までの大きな窓からウッドデッキに出ることができ自然を楽しむことができます。


設計事務所orハウスメーカー
ハウスメーカーや建設会社に依頼するのと違い施工から切り離された設計事務所でなければできないことがあります。 設計事務所に依頼するメリットをいくつかあげてみますので依頼先を迷っている方は参考にしてください。 01 設計事務所のノウハウが詰まった図面がある ハウスメーカーや建設会社の場合は両手で(場合によっては片手で)数えられる程度の図面で家をつくっているところが多いように感じます。ある程度標準化されているからそれでも大丈夫なのかもしれませんが、それではこだわった家はできないように思います。 一方、私たちが設計図を作るとかなり多くの枚数になります。(標準的な木造2階建ての住宅でA3の図面が50~70枚ぐらいになります)意図した建築をつくろうとするとどうしてもそれぐらい必要になってしまいます。 つまり、設計事務所のノウハウが詰まったしっかりした図面で家づくりを行うことができます。 02 しっかりした対応ができる 普通に考えてハウスメーカーや建設会社のスタッフである設計者や外注された設計者はその会社の標準的な設計と違うことはできないし、見積りに口をはさむ


考えること
「土地」の上に建物が建ち、「建物」の中に人が住み、そこに「人」の生活が生まれます。 恵まれた環境ではそれを十分いかし、そうでないときはその難条件を克服し、その人や土地にあった建築をつくりたいと考えています。 設計にあたって考えることを人・建物・土地の3つの要素に分けて書き出してみました。 01 「人」のこと [年齢] 家族は年がたつにつれてそのライフスタイルが変化していきます。今から5年後、10年後、20年後、30年後...に家族のライフスタイルがどう変化していくのか考えておく必要があります。それをふまえて、現在の生活を楽しく充実したものにするためにどのような建物を用意しておくか考える必要があります。 [続柄] 家族構成が二世帯や三世帯になる(あるいは将来そうなる)場合はプライバシーをどの程度とるのか見極めることが重要です。完全に分離して造るか?、風呂は一緒にするか?、食事は一緒にするか?、たまにみんなが集まれるスペースがあればいいか? ご主人の親か奥さんの親かによってもかわってきます。 [職業(学年)] 職業(学年)によって生活の様子(起床・就


お施主さんへのお願い
ご自身の夢を形にするにはやはりご自身がよく考えてどのようなものを作りたいかを私に伝えていただくことが大切です。 文章にして伝えていただく、言葉で伝えていただく、あるいは、はっきりとした言葉ではなくても会話の端々で建築に対する思いみたいなものが私に伝わればそれを形にしていく中で満足していただける建築ができてきます。 会話の中からお施主さんの望む姿を見出すのも仕事のうちと思って取り組んでいますが、やはりはっきり伝えていただかないとわからないこともあります。(人間だもの・・・) 医者に行ったときに症状を伝えないと治療に移れないのと同じで、夢を実現するためにご自身の考えをいろいろ話してください。最初は違っていても全然かまいません。話し合いの中で修正していけばよいのでどんどん希望を私にぶつけてくださいね。 完成した時に「思ったとおりの家ができました!ありがとうございます。」という嬉しいお言葉をいただくことがありますが、それは施主さんが思いをしっかり私に伝えてくださったおかげだと思っています。


職人さんたちとの関係
多くの建築業者さんは私たちのことを「先生」と呼んでくれます。 若いころは「先生なんて呼ばないで」などといちいち言っていましたがこのごろはあだ名(?)みたいなものと考えてそのままにしていますが本当は「久松さん」など名前で呼んでもらいたいです。 どんなに素晴らしい図面を作っても職人さんたちの力を借りないと実現しません。 職人さんや現場監督さんの技術力に敬意を表しつつ、いい意味で対等な立場で一緒に建築を作り上げたいと思っています。(偉そうにしていても良い建築はできないです。) 「先生」を演じる(?)場面があるとしたら(あまりないですが)職人さんが明らかに手を抜いた仕事をした時に施主さんの代わりに怒ってやり直してもらう時くらいでしょうか... それなりに経験を積んでいるので手抜きなのか一所懸命やったけどうまくいかなかったのかはわかるつもりです。 前者のケースでは結構マジで怒ります。 後者のケースではもちろん怒りませんが施主さんに喜んでもらうために頑張ってやり直すようお願いします。
bottom of page